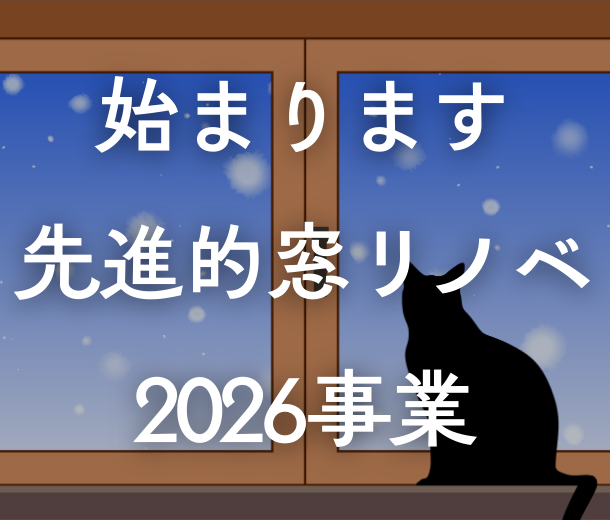住宅兼用施設新築工事 ~羽目板とは??加工から取付まで~
焼津市の住宅兼用施設新築工事現場で内壁工事が行われている間にヤマタケの工場では羽目板(はめいた)の加工が進んでいました。
羽目板とは、壁や天井に連続して並べ張り合わせる板のことです。
羽目といえば「羽目を外す」=「調子に乗って度を超すこと」「節度を失うこと」を連想しませんか?
羽目を外すという言葉の由来は、①今回の建築の羽目板からきている説②馬にくわえさせて乗っている人の意思を伝えるハミからきている説があります。
①の理由は、綺麗に並べた羽目板を外すと建物が台無しになる。
②の理由は、ハメを外すと馬をコントロールできなくなる。
このことから「羽目を外す」という表現をするようになったとか…どちらも言われてみれば納得。
先日の柱の番付の記事での「いの一番」の語源といい、建築にかかわる言葉がたくさんありおもしろいですね。
今回はこちらの現場での羽目板の加工風景から取り付けるところまでを見ていきます。
プレーナーにかけて表面を平滑に整えた杉板の側面に、板と板を組み合わせるための「相(あい)じゃくり加工」をしていきます。

相じゃくり加工は水が溜まりにくいため外壁に多く用いられます。
さらに目透かし加工をすることによって板と板の間に意図的に隙間ができる仕上がりになります。(↓写真右側の下端が左側より広く切り取られているのがおわかりいただけると思います)
この隙間は意匠的なことだけではなく無垢材特有の伸縮を吸収させる効果もあります。


ちなみに側面を凹凸に加工する接合方法は「本実(ほんざね)加工」と呼びます。凹のくぼみに釘やビスを打つため、釘やビスを表面に見せずに接合させることができます。相じゃくり加工と並んで代表的な実加工です。同じく凹の下側を長くして目透かし加工をすることもあります。併せてぜひ覚えておきましょう。
続いて、「死に節(しにぶし)」があれば埋め木を行います。死に節とは枯れた枝が幹に巻き込まれてできる節のことです。周りの組織とつながりがなく抜け落ちる可能性があるため、穴をあけて別の木材を丁寧に埋め込み修復します。この方法を「埋め木」と言います。
埋め木の様子は→こちらのブログより、もしくはこちらのブログより
(↓死に節)

(↓木を埋め乾燥中)

(↓しっかり乾燥したら切り取り、平に均して埋め木完了)

続いて、塗装作業に入ります。




しっかり乾燥させていよいよヤマタケの工場から出発します。


現場では役物(やくもの)の施工が完了しています。
役物とは屋根や外壁に用いられる規格外・定尺外の特殊な形状の板金部材のことです。



いよいよ外壁に羽目板が取り付けられました。




引き続きガルバリウム鋼板の施工が進んでいますので、施工の様子をまた後日お知らせします。
外部に羽目板を使った施工例をいくつか載せておきます。
内部までたっぷり羽目板をつかった家もありますのでリンクより施工例をご覧ください。








引き続き工事の様子をお知らせします。