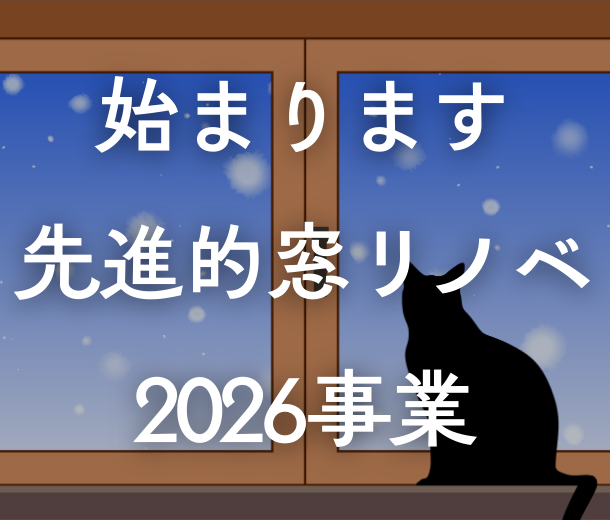神社拝殿新築工事 ~竿縁天井(さおぶちてんじょう)・ 床刺し(とこざし・とこさし)とは?~
前回廻り縁を施工していた藤枝市の神社拝殿新築工事現場では竿縁天井(さおぶちてんじょう)の施工が始まりました。
暑い現場です。熱中症対策にも気を配りながらの作業です。

廻り縁に通す竿縁天井の竿縁を加工。

吊り木、野縁受け、野縁、竿縁を施工。



天井板を渡していきます。




天井が張れました。




この天井形式を「竿縁天井(さおぶちてんじょう)」といい、日本建築で一般的に用いられています。竿淵天井、棹縁天井と表記されることもありますが、いずれも同じ構造を指します。
竿縁と呼ばれる細長い材の上に天井板を渡して支えます。
ここで和室における天井のルールについてご紹介します。
竿縁は床の間と平行に施工します。
床の間に直角方向に取り付けた状態は「床刺し(とこざし・とこさし)」と言われタブーとされています。床挿し・床差しとも書きます。
和室の中で最も格式高い場所は床の間です。そこに竿縁が刺さる状態で施工されることは昔から不吉とされ避けられてきました。
武家屋敷には床刺しの部屋があり、切腹に使用されていたとか。
また竿縁のない目透かし天井であれば天井板の目地が直角になっている状態は「床刺し」にあたります。畳も同様で、床の間の前の畳が直角に入る敷き方は「床刺し」にあたり、どこの家でも平行に敷かれているはずです。
ご自宅の和室もぜひチェックしてみてください。
ちなみに、石川県金沢市の兼六園の成巽閣(せいそんかく)越中の間は床刺しになっているのですが、一部を三角の網代張りにして床刺しの凶相を防いでいるとか…おもしろいですね。
ただ、和室にも今ではいろんなデザインがありあえての床刺しもありますが、和室をご検討中の方はぜひ覚えておいてください。
新築施工例(伊太の家)より。竿縁が床の間と平行になっています。

リフォーム施工例(小土の家)より。目透かし天井が床の間と平行になっています。

リフォーム施工例(末広の家)より。床の間の前の畳は床の間と平行に敷かれています。

リフォーム施工例(茶町の家Ⅰ)より。床刺しを避けつつ遊び心のある和室。



天井に引き続き、床張りの工事に取り掛かります。

外部では塗装工事に入りました。







引き続き工事の様子をお知らせします。